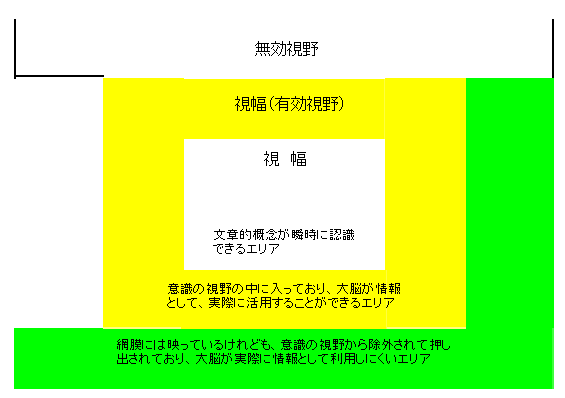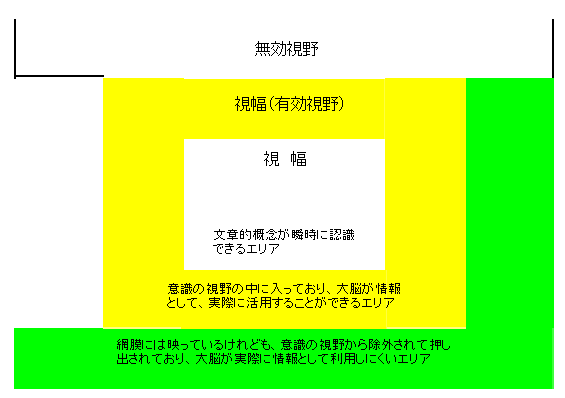視野の拡大は日常生活の心構え 視野の拡大は日常生活の心構え |
| |
| 有効視野が狭かった人は、日常生活で有効視野を広げるトレーニングを積むことも必要になってきます。たとえば、道を歩いている時に、ただ前方を見て歩いているだけでなく、同時に両側も見るようにし、できればその際、両側の店の看板の文字を同時に読むようなことも試みるのです。また、道路を横断する時も、できるだけ視野を広げ安全を確認するのです。 |
| |
| それから、本などを読む時も、ページ全体の文字を一度に視野に入れることを心がけてください。この場合、意味は読み取れなくても、さしつかえません。とにかく全文字を視野に入れる、決して視野を絞り込まない習慣を身につけることが、大事なのです。最初のうちは、これまでの習慣にないことですから、やっていて違和感が伴います。しかし、要するに“習うより慣れろ”で、やがて新しい習慣が見につき、有効視野も除々に広がってきます。 |
| |
| たとえば、麻雀をやっていて最初から盲牌のできる人はいませんし、盲人用の点字なども、最初から指先で読み取れる人はいません。これも、訓練と練習を続けることによってできるようになるのですが、“習うより慣れろ”は大脳生理学的に見ると、大脳の中にそれを読み取るための回路が新たに編成されたということです。 |
| |
| たいていの生物では、生まれてから短期間の内に大脳の回路ネットワークが決まってまい、新たな回路を編成するような余地が残らないのですが、脳細胞数の多い人間の場合には、それが可能なのです。潜在能力をフルに発揮するためには、この特性を最大限に活かさなくてはいけません。有効視野を広げる訓練は、心がけて練習していると、だいたい1ヶ月ぐらいから成果が見えてくるようです。 |
| |
 文字と景色の視野の差 文字と景色の視野の差 |
| |
| さて、有効視野は、そのエリアに入った事物は情報として「認識できる幅」ということで、視幅とも呼びます。ところが、その情報が文字で構成されていると、意味まで全部を読み取れるわけではありません。つまり「全部の文字を認識できる」ということ。「文章として意味を理解できる」ということの間には、ギャップがあるのです。もちろん、時間をかけて観察していれば、有効視野内の文章の意味は理解できるようになりますから、パッと瞬間的に見た時に、という条件を付けての話です。具体的には1秒です。 |
| |
| この「瞬間的に文章としての意味まで理解できる範囲」を“概念まで認識できる幅”ということで識幅と呼びます。当然、識幅は視幅の中に含まれ、最終的には、この識幅が広げれば広いほど能力が高いことになります。下記の図のように関係になります。 |
| |
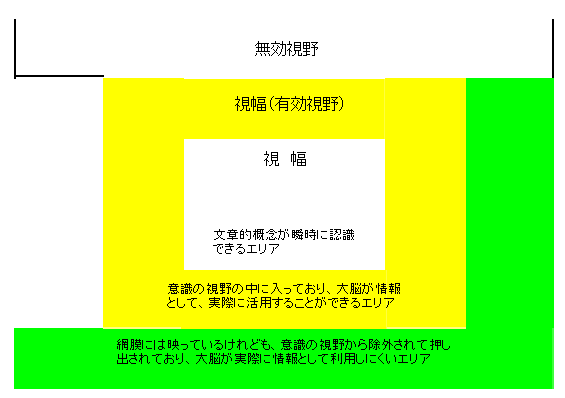 |
| |
| 文字というのは、いくら全体的に捉えられたとしても、最終的には端から順番に読み取らなければ意味不明になる点で直列方式の情報の典型です。また、左脳の言語野を活用して論理的に分析しなければ、意味不明になる点で、最終的には左脳が主導権を握るものです。この点で、意味の順番がなく、全ポイントとランダムに見ればよいという景色とは、性質が異なります。それでも、視幅および、識幅を拡大していく訓練、視野を狭める条件反射を克服する訓練を続けていれば、限りなく両者のギャップを埋めていくことができます。 |